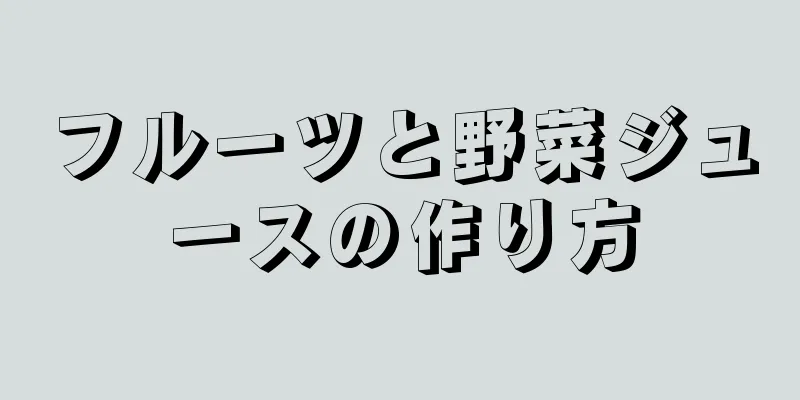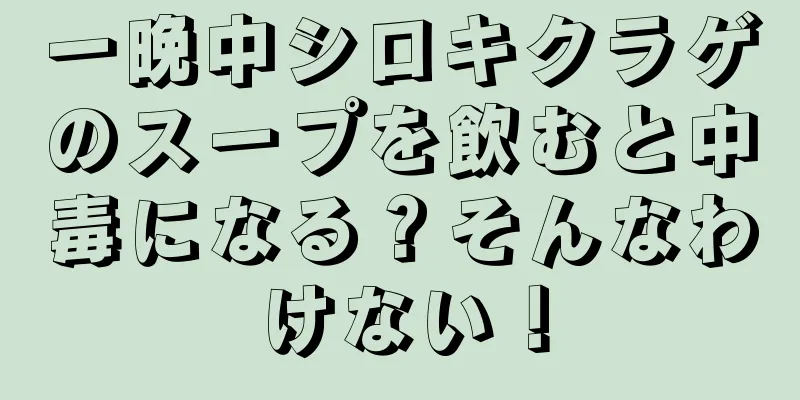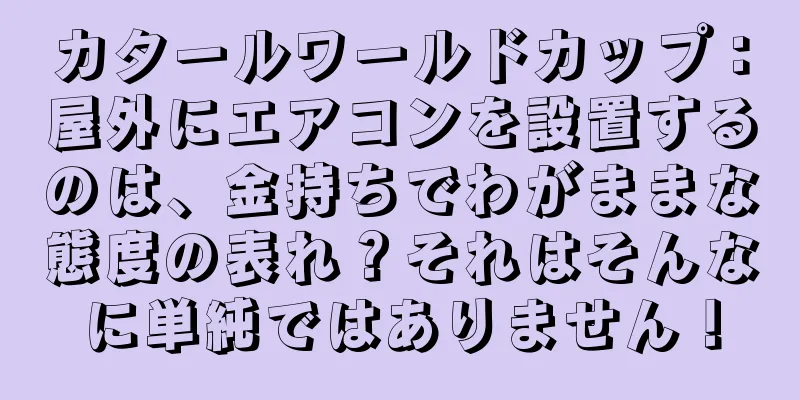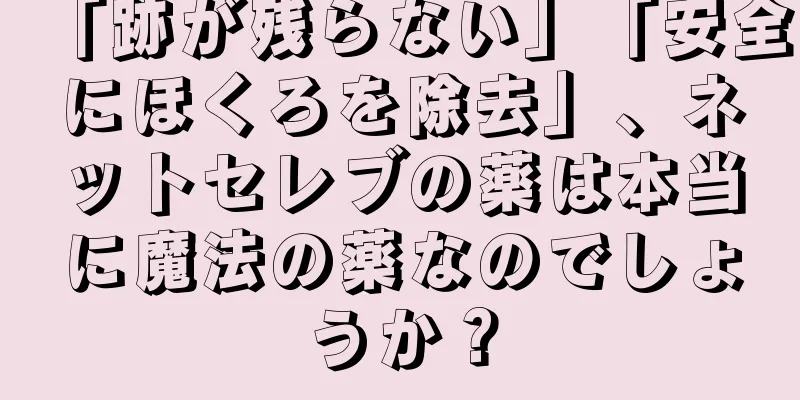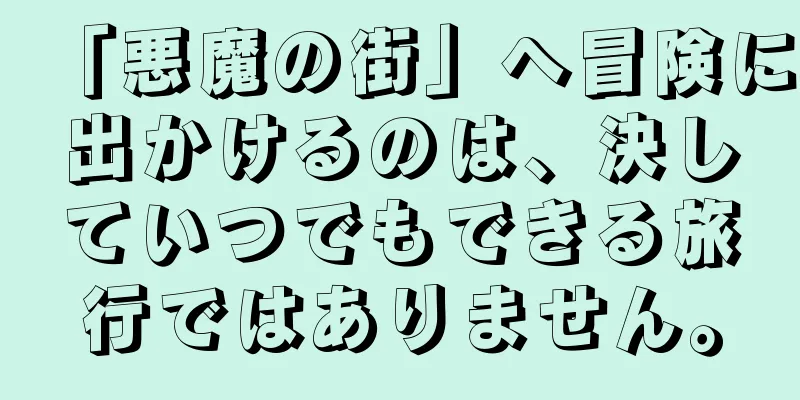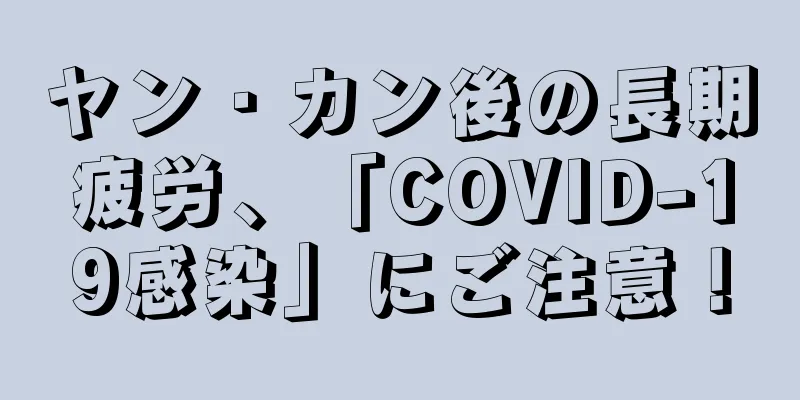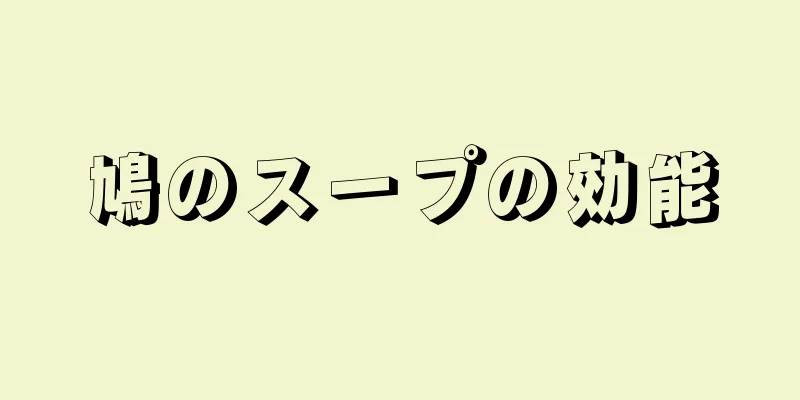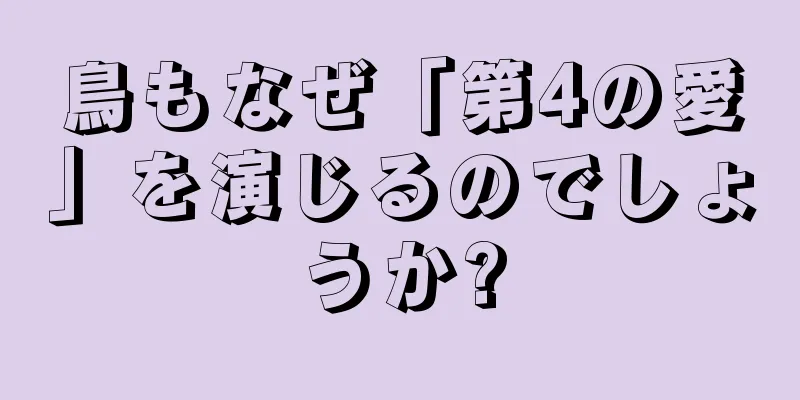道のない道を作るのは難しい:緑色蛍光タンパク質の伝説的な発見の旅
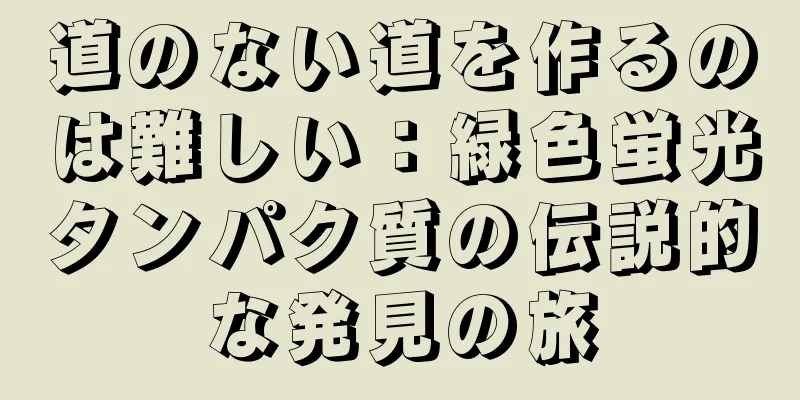
|
緑色蛍光タンパク質は自己触媒によって発色団を形成し、青色光や紫外線の刺激を受けて緑色蛍光を発します。遺伝子工学や他のタンパク質との融合により、目に見えないタンパク質を可視化することができます。そのため、過去 20 年間、生物学者や医学者が細胞内のさまざまな生化学的プロセスを研究するためのガイドとなってきました。生物学研究にとって重要なツールといえるでしょう。その最初の発見とその後の重要な発展は2008年のノーベル化学賞を受賞し、それに身を捧げた科学者たちの探究の旅は科学史上伝説的な物語とも言えるでしょう。 著者 |徐一勲 生命科学の歴史は、観察しやすいマクロレベル(種の分類や肉眼解剖学など)から、観察に器具を必要とするミクロレベル(顕微鏡解剖学で研究される組織や細胞など)へと発展してきました。 17 世紀、オランダの科学者アントニー・ファン・レーウェンフックは、改良した光学顕微鏡を使用して初めて単細胞生物を観察し、記述しました。これは生物学の歴史における画期的な出来事でした。生物学者は顕微鏡の助けを借りて、これまで存在が知られていなかった細菌、細胞、細胞小器官などの微視的な研究対象を徐々に観察してきました。このような還元主義的な研究が分子レベルに達すると、電子顕微鏡であっても、生きた細胞内のタンパク質などの生物学的高分子の発現や局在を直接観察することは難しくなります。ビクトリアクラゲ(Aequorea victoria、以下クラゲまたはクラゲと略す)から分離された緑色蛍光タンパク質(GFP)により、これまで見えなかったタンパク質が可視化されました。過去 20 年間、それは生物学者や医学者にとって細胞内のさまざまな生化学的プロセスを研究するための指針となってきました。この記事では、GFP によってもたらされた生物学革命に重要な貢献をした数人の科学者の物語を紹介します。 生物発光の初期研究 GFP の発見は生物発光現象と密接に関連しているため、まずはさまざまな種類の低温発光を紹介する必要があります。 図1: 低温発光現象の種類とその励起モード 火は人類史上最も重要な発明であり、それに関連する白熱は通常、物体が高温に加熱されたときに放出される可視光として定義されます。低温発光は、環境と熱平衡状態ではない励起された化学成分によって自発的に放出される可視光の一種です。 2,500年以上前、古代ギリシャの科学者アリストテレスは著書『色彩について』の中で、「火ではない、火の発生とは何の関係もない物体が、自然に光っているように見えることがある」と書いています。これは、人類が白熱発光と低温発光の重要な違いを長い間認識していたことを意味します。白熱電球は照明効率が悪く、電気エネルギーのごく一部しか光エネルギーに変換できず、残りのエネルギーは熱の形で消散します。一方、生物発光は化学エネルギーを光エネルギーに変換する過程でほとんど熱を発生しない効率的な化学反応であるため、「冷光」とも呼ばれます。 異なる励起モードに応じて、低温発光は、光発光、電界発光、化学発光(生物発光は化学発光の特殊な種類)など、多くの種類に分類できます(図 1)。最も一般的な発光は蛍光と燐光です。読者は蛍光と生物発光の違いに特に注意することをお勧めします。 自然界で最も一般的な生物発光現象の一つはホタルです。毎年夏の夜になると、ホタルが草むらで舞い、幻想的で美しい光景を作り出します。唐代の偉大な詩人、李白はかつて「蛍歌」という詩を書いた。「蛍は雨に打たれても消えず、風に吹かれてより輝きを増す。もし天に舞い上がれば、きっと月の隣の星となるだろう。」 図 2: 生物発光の研究は、科学者がホタルの現象に魅了されたことから始まりました。 自然界にはホタル以外にも、細菌、原生動物、菌類、クラゲ、イカなど、低温で光る能力を持つ種が数多く存在します。科学者たちは長い間、生物発光現象に興味を抱いてきましたが、効果的な科学的研究方法がありませんでした。 1667年になって、イギリスの化学者ロバート・ボイルが空気ポンプを使ってベルジャーから空気を抜き、内部の菌類が光らなくなったことを発見しました。空気を再び取り入れると、菌類の生物発光能力が回復した。 17 世紀の化学の世界では、人々は空気の組成について何も知りませんでした。 1770 年代になって、スウェーデンの化学者カール・ヴィルヘルム・シェーレとイギリスの化学者ジョセフ・プリーストリーがそれぞれ酸素を独立して発見し、最終的にフランスの化学者アントワーヌ・ラボアジエによって解明されて初めて、生物発光が酸素に依存していることがようやく明らかになりました。 生物発光の化学的メカニズムの探究は、1世紀以上にわたる停滞の後、フランスの生理学教授ラファエル・デュボアの登場により新たな転機を迎えました。 1885 年の実験で、デュボアは最初に試験管内でコメツキムシ (Pyrophorus) の発光組織を冷水で均質化し、抽出物が短時間光り、その後暗くなることを発見しました。沸騰したお湯を使って採取した組織抽出物は全く光りませんでした。驚いたことに、冷却した温水抽出物を、光らなくなった冷水抽出物に加えると、混合物は実際に再び光りました (図 3)。デュボア氏が冷水抽出物の輝きを保ち続けたい場合、冷却した温水抽出物を絶えず追加する必要がありました。 図 3: 1885 年にデュボアが「ルシフェリン-ルシフェラーゼ」の生物発光の原理を初めて発見した有名な実験 [Pieribone, V. & Gruber, DF (2005) Aglow in the Dark: The Revolutionary Science of Biofluorescence, Belknap Harvard.] デュボイスはその後、ホタルを含む他の発光生物でも同様の実験結果を得て、2つの重要な結論に達した。(1) 生物発光反応には酸素に加えて少なくとも2つの化学成分が必要である。 (2)発光反応における「燃料」成分は沸騰水の高温に耐えられるが、「点火装置」や触媒は耐熱性がない。デュボアは、ローマ神話のラテン語「ルシファー」(文字通り「光の使者」)を借用して、2 つの成分に名前を付けることにしました。熱に不安定な触媒はルシフェラーゼと名付けられ、耐熱性の小分子はルシフェリン(フランス語:ルシフェリン、英語:ルシフェリン)と名付けられました。 その後の多くの生物学者による研究により、多くの発光種において、ルシフェラーゼは異なるタンパク質配列を持ち、ルシフェリンも多様な有機小分子構造を示すものの、「ルシフェリン-ルシフェラーゼ」の生物発光原理は有効であることが示されました。生物発光研究者の目標は、興味のある発光種を選択し、生化学的手法を使用してさまざまなルシフェリンとルシフェラーゼを分離および精製するという具体的なものになります。科学者たちはホタルの発光システムに関する徹底的な研究を通じて、酸素、ルシフェリン、ルシフェラーゼに加えて、ATP と Mg2+ イオンも必要な条件であることを発見しました (図 3)。 生物発光は陸生種では珍しいですが、深海では海洋生物の 90% 以上が生物発光することができます。海抜から 75 メートル下がるごとに太陽光の強度は 10 分の 1 に減少します。太陽光が届かない深さでは、発光動物は餌を見つけたり、捕食者から逃げたり、交尾相手を引き付けたりするのに明らかに有利です。ホタルの発光メカニズムを大まかに説明した後、多くの科学者は海洋発光生物に注目しました。最も有名なのは、米国プリンストン大学の学校の創設者であるハーベイ教授(E. ニュートン ハーベイ)です。 1916年、当時28歳だったハーヴェイは妻とともに新婚旅行で日本へ行きました。三崎臨海実験所付近の海は、2人が夜泳ぐのに適している。ハーヴェイは泳いでいるときに、Vargula hilgendorfii(以前はCypridinaとして知られていた)と呼ばれる光る海洋生物に魅了されました。ウミホタルは採取して乾燥させると長期間保存でき、水に濡らすと再び光ります。そのため、ハーヴェイはこれらを、生化学的手法を用いて生物発光を研究するための最良の実験材料とみなしています。ハーヴェイの研究室は、ホタルの発光システムはホタルの発光システムよりも単純であることを発見した。ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酸素のみが必要であり、ATP と Mg2+ イオンは必要ありません (図 4)。しかし、ハーヴェイ氏のチームはウミホタルからルシフェリンを部分的に精製した後、20年以上懸命に研究を重ねたが、結晶を得ることはできなかった。高純度のルシフェリンがなければ、分子構造を解明してウミホタルの発光の化学的メカニズムを詳細に研究することはできない。 図4: ウミホタルのルシフェリン-ルシフェラーゼ発光システム 下村脩がホタルからルシフェリンを結晶化して精製 ホタルのルシフェリンを完全に精製することが困難だったことが、GFP物語の最初の主人公である下村脩が歴史の舞台に立つ機会を与えた。同じく1928年生まれのジェームズ・ワトソンと比べると、下村脩の「人生のスタートライン」は、後者の単なる「ネガティブコントロール」であり、波乱万丈だ。下村脩は父親が軍人だったため、主に長崎県諫早市に住む祖母に育てられた。 1941年4月、諫早中学校1年生になったばかりの下村脩と同級生たちは、同年3月に日本政府によって改正された国家総動員法に基づき、軍事訓練に参加しなければならなかった。 1944年秋、中学3年生になると、学校は定期的に授業を休校し、大村市内の軍用機修理工場で奉仕労働を義務付けるようになった。米軍はすぐにこの軍需工場に狙いを定め、20機以上のB-29爆撃機を派遣して完全に破壊した。下村脩の同級生のうち、十分に速く走れなかった数人が残念ながら亡くなった。 諺にもあるように、「幸運は決して単独ではやって来ず、不幸は決して単独ではやって来ない」。 1945年8月9日午前10時57分、長崎市は不幸にも米軍の2発目の原子爆弾の攻撃を受けました。当時、下村脩と数人の同級生は長崎の中心部から15キロ離れた別の軍需工場で働いていた。おなじみの空襲警報が鳴ると、彼らは落ち着いて工場から出て、近くの丘に登って様子を伺いました。下村脩さんは、B-29爆撃機が市の中心部に向かって南に飛行し、3つの貨物用パラシュートを投下するのを目撃した。後に、これらは原爆投下から、彼らが目撃しなかった最後の爆発までの間に「グレート・アーティスト」航空機によって投下された3台の無線高高度気象測深機であったことが判明した。この時、誰もが爆撃は大きな脅威ではないと誤解し、工場に戻って仕事を続けようと決心しました。彼らが座るとすぐに、窓の外の強い閃光が学生たちの目を30秒間一時的に見えなくし、続いて大きな爆発音が鳴り、気圧が急激に変化しました...軍需工場と長崎の間の距離が、下村脩と彼の友人たちの生存の鍵であったことは明らかです。 第二次世界大戦は日本の降伏で終わったが、17歳の下村脩は依然として将来に希望を見出せなかった。建海中学校では原爆の爆発により多くの教師と生徒が死亡し、生徒のファイルもすべて破壊されたため、近年の中学生は正常に卒業することができませんでした。下村脩さんは、2年連続で高等学校(日本語:高徳学校)または専門学校(日本語:高徳公業学校)に出願したが、中学校の成績証明書を提出できなかったため不合格となった。 1948年4月になってようやく下村脩は薬学部に入学することができたが、原爆の爆発による多数の死傷者により長崎医科大学の教員と学生の再建が緊急に必要となったため、彼は薬学部に興味がなかった。(図5)これが当時彼が高等教育を受ける唯一の機会でした。 図5: 1948年の長崎薬科大学の仮校舎 廃墟の上に再建されたばかりの長崎医科大学には、教育資源が極度に不足していた。当初の教授20人のうち12人が原爆の爆発で死亡し、4人が重傷を負った。薬学コースの教育業務のほとんどは、経験の浅い講師によってのみ遂行可能です。教育資金が限られていたため、下村脩は学部3年間で分析化学と物理化学の研修に集中し、有機化学を学んだり有機合成実験を行ったりする機会はほとんどありませんでした。下村修氏の分析化学の教師である安永俊吾氏は、すぐに生徒の優れた実践能力に気づき、キャピラリークロマトグラフィーを使用した分離と精製を研究するために、いくつかの試薬を家に持ち帰ることを許可しました。この研究の結果、下村脩は1953年に安永教授との共著で日本語で最初の学術論文を出版するに至りました。 1951年3月、下村脩は長崎薬科大学を首席で卒業し、武田薬品工業に就職を希望したが、面接官は彼の性格が企業環境での成長には向かないと率直に指摘した。安永教授は、やがて下村脩に援助の手を差し伸べ、分析化学の助教として学校に残るよう招いた。下村脩は将来の人生について明確な計画を持っていなかった。彼はただ自分の仕事をすることに集中しており、より高い学位を取得するために大学院に進学することなど考えたこともなかった。安永教授は下村脩氏のもとで4年間働いた後、他の研究機関を訪問する1年間の有給学術訪問の機会を彼に確保しました。 安永教授は下村脩氏のキャリアにおける最初の後援者として、彼に適した訪問研究室を見つける手助けも積極的に行いました。エルンスト氏の日本の化学界における人脈は主に名古屋大学にある。下村氏は、生化学を専門とする江上不二夫教授こそが、下村氏の科学研究の視野を広げるのに最適な人物だと考えている。日本の電話通信システムは戦後何年もの間完全には復旧されなかった。安永教授は自ら下村脩氏を連れて長崎から名古屋まで10時間以上も電車に乗らなければならなかった。なんと、その頃江上教授は学会に出ていて、会うことができなかったのです。偶然の出来事が歴史の発展の軌道を変えた例は無数にあります。もし下村脩が江上教授と出会い、研究室に入ることに成功していたら、読者は今この興味深い物語を読んでいなかっただろう。その後、二人は有機化学者の平田義正教授を訪ね、数分間の短い会話の後、平田教授は下村さんにいつでも客員学生として研究室に来てほしいと歓迎した。 1955年4月、平田教授は真空デシケーターを指差して、研究室に来たばかりの下村脩にこう言った。「ここには乾燥したウミホタルが大量にあります。この海生動物はルシフェリンとルシフェラーゼの相互作用によって光ります。ウミホタルのルシフェリンは非常に不安定で、酸素に触れると分解してしまいます。このルシフェリンを精製して結晶化してみませんか。」下村修は、この難しいテーマが平田教授の大学院生には適していないことを知っていました。訪問学生だった彼には学位取得の重荷はなく、「生まれたばかりの子牛」のようなリラックスした態度で大胆に挑戦しようと決心した。 1935年、ハーヴェイ研究室のルバート・アンダーソンは、この非常に不安定なルシフェリン部分を約2,000倍精製し、吸光分光法によってその分子構造中のアミノ酸成分を推測できる2段階抽出法を発明しました。これを基に下村脩は、結晶純度のルシフェリンを得るためには、出発物質として少なくとも500グラムの乾燥したウミホタルが必要であると計算しました。これはハーヴェイの研究室で使用されている量の10倍に相当し、巨大なソックスレー抽出器を製作する必要がありました(図6左)。 図6:10か月の努力の末、下村脩は1956年にウミホタルからルシフェリンの精製と結晶化を完了しました(白黒写真では結晶の実際の深紅色は表現できません) 下村脩氏は、困難な科学的研究の中で、窒素や不活性ガスを使用するだけでは、抽出システム内の微量酸素によるルシフェリンの消費を排除するには不十分であることを発見しました。微量の酸素が液体の水に変換され、硫酸に吸収されるように、水素をシステムに送り込む必要がありました。化学者なら誰でも、水素の取り扱いを誤ると爆発を引き起こす可能性があることを知っているので、平田研究室の他のメンバーは、下村脩が激しい実験を行っている間は彼からかなりの距離を保っていた。水素の利用は下村脩に画期的な進歩をもたらしたが、さまざまな方法で水素を結晶化しようとする試みは常に失敗していた。結晶化前の抽出物を準備するたびに、彼はほとんど眠らずに一週間連続して作業する必要があり、失敗すると、抽出物は廃棄される前に簡単な成分分析を行うことしかできませんでした。決して諦めない下村脩は、平均して毎月1週間はこのように苦労を重ねたが、1956年2月のある夜、再び失敗に直面しそうになった。彼は家に帰る前に、捨てようとしていた抽出物に同量の濃塩酸を加えることにした。黄色の溶液が濃い赤色に変わった後、彼はそれを一晩研究室のベンチに置き、翌日、その中にどんなアミノ酸が含まれているかを検出する準備をしました。 朝、下村脩が研究室に戻ると、溶液が濃い赤色から無色に変わっていた。彼の最初の考えは、塩酸がルシフェリンの加水分解を引き起こした結果であるというものでした。すると、試験管の底に少量の黒い沈殿物があり、顕微鏡で詳しく調べたところ、実はそれが赤い針状の結晶であることがわかりました(図6右)。これらの結晶は、ウミホタルのルシフェラーゼ抽出物と混合すると光ることができ、ルシフェリンの結晶化が成功したと正式に宣言されました。振り返ってみると、ルシフェリンの構造が未知であった時代に濃塩酸がルシフェリンの結晶化を促進したという事実は、偶然の発見に他ならない。さらに、その夜は平田研究室のガス炉が止められ、溶液の温度が一晩中室温で下がり続けたことも結晶化の過程を助けた。 「天国は努力する者に報いを与えるだろう。」 10か月にわたる科学研究の努力の末、下村脩は予想外の進歩を遂げました。平田教授は、ハーヴェイの名古屋大学への学術訪問も1年間延長し、1957年にハーヴェイの最初の英語の学術論文が無事出版されるよう尽力した。ハーヴェイ教授の後任であるフランク・ジョンソンは、当時、米国のプリンストン大学の教授であった。この論文を読んだ後、彼は、ハーヴェイ学派を20年以上悩ませてきた難問が、学士号しか持っていない若い日本人学者によって解決されたことに驚かずにはいられなかった。この稀な成功は、下村脩のキャリアにおいて重要な機会をもたらした。1959年春、長崎薬科大学に戻って間もなく、ジョンソン教授から、翌年の秋から3年間プリンストン大学の客員研究員として働くよう招待する手紙を受け取ったのである。 下村脩と発光クラゲとフライデー ハーバーとの切っても切れない絆 下村脩は1960年9月にプリンストン大学に着任しました。ジョンソン教授は彼に、研究室が現在最も興味を持っているのは発光クラゲの研究であり、ウミホタルの発光研究の成功を弾みにしてクラゲの発光メカニズムの研究で画期的な成果を挙げてほしいと伝えました(図7)。十分な実験材料を得るために、当時アメリカで唯一捕獲できた場所は、毎年夏に大量のクラゲが捕獲できるワシントン州サンファン諸島のフライデーハーバーの海域でした。 図 7 出典: Chalfie, M. (2008) Nobel Lecture. 1961年以来、ジョンソン氏と彼の研究チームの主要メンバーは、ほぼ毎年夏に、各自の機材を持ち込み、プリンストンからフライデーハーバーまで7日間かけて車でクラゲを採集してきた。生化学的手法を用いてクラゲの発光を研究するために、研究者らはまず、回収されたクラゲの傘膜を大量に手作業で切り取り(図8)、地元のワシントン大学支部の実験室環境を利用して、傘膜の端にある発光器官の絞り出した液体(スクイーズ液)を凍結して保存する必要がありました。 図 8: 北米西海岸に生息するオワンクラゲと、その傘の端にある生物発光器官。出典: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-chemistryprize2008.pdf 島での下村脩氏とジョンソン氏にとって、最初の1週間の調査は順調なものではなかった。彼らはデュボアの「ルシフェリン-ルシフェラーゼ」の考えに従いましたが、耐熱性と耐熱性の2つの成分を分離することができませんでした。この時、若き下村脩は、デュボアの理論に固執する必要はなく、何の仮定もなしにクラゲの発光物質を分離できると感じていた。しかし、ジョンソンはデュボアの理論を放棄して考えを変えることを望まなかった。なぜなら、デュボアの理論は長年にわたり、複数の発光種において例外なく繰り返し検証されていたからだ。教師と生徒は自分の意見を主張し、妥協を拒否したため、実験台の反対側に座ることしかできませんでした。雰囲気はかなり緊張して気まずいものでした。 下村脩氏は、研究中に問題に遭遇するたびに、実験を一時停止し、静かな場所を見つけて新しいアイデアについて熟考することを好みます。フライデー ハーバーでは、小さなボートに乗って、人里離れた無人の海域に行くことができます。下村脩は数日連続で海に漕ぎ出し、その後は一人船の中で目を閉じて考えていた。船が風と波に流されるにつれ、彼は何度か眠りに落ちた。ある日の午後、下村氏は船の中で昼寝から目覚めると、突然、あるアイデアを思いついた。クラゲの生物発光はルシフェリンやルシフェラーゼとは関係ないとしても、タンパク質はやはり必要だろう、と。タンパク質の活性は pH に敏感です。溶液のpH値を調節することでクラゲの発光を可逆的に抑制することは可能ですか?下村脩はこの時とても興奮していた。彼は一生懸命に漕いで研究室に戻り、pH値の異なる緩衝液をいくつか用意しました。 pH値が7、6、5のときでも、クラゲ抽出物は弱い光を発することができました。しかし、pH値を4に調整すると、溶液の弱い光は消え、酸性度が発光物質を阻害する可能性があることがわかりました。重炭酸ナトリウムを使用して pH を中性に戻すと、弱い光が再び現れ、酸性の阻害効果が実際に可逆的であることが示されました (図 9)。 図9 出典:下村 修(2008)ノーベル講演 この進歩に下村脩氏は非常に興奮したが、抽出物がなぜ弱い光しか発しないのかについては依然として困惑していた。このとき、下村脩の「覚悟」に、彼のキャリアで二度目の、つかみどころのないチャンスが訪れた。 1961年のある真夏の夜、遅くまで一人で作業をしていた下村脩は疲れ果てていた。彼は、酸を中和したクラゲのエキスはあまり役に立たないと感じたので、それをシンクに流し込み、その日はそれで終わりにした。電気を消して立ち去る前に、彼は無意識に振り返って、抽出液を注いだばかりのシンクから明るい青い光が発せられているのを見て驚きました。思慮深い下村脩氏は、この現象の背後にある理由を分析し始めました。 2日目、近くの水槽の海水も同じ水槽に流れ込んでいることに気づき、海水中の何らかの物質がクラゲエキスの弱い光を刺激して強い光に変えているのではないかと仮説を立てました。この考えに沿って、下村脩氏は「加減法」を用いて海水中の高濃度イオン成分を一つずつ調べたところ、カルシウムイオンがクラゲ抽出物中の発光タンパク質を瞬時に刺激できることを発見しました。ジョンソン教授は、下村脩がカルシウムイオンの役割を発見した画期的な成果を目の当たりにして、自分の科学研究能力に絶対の自信を持つようになりました。 カルシウムイオンが発光開始剤としての役割を理解した後、下村脩は pH を調整する必要がなくなりました。代わりに、有名なカルシウムイオンキレート剤である EDTA を抽出物に加えるだけで、発光タンパク質をより効果的かつ可逆的に阻害し、さらなる分離および精製プロセス中にターゲットタンパク質が発光によって失われないようにしました。 1961 年 8 月末までに、ジョンソンのチームは 10,000 匹以上のクラゲを収集し、EDTA を含む粗抽出物を作成し、それをドライアイスで凍結しました。彼らはそれらすべてをプリンストンに持ち帰り、体系的なタンパク質精製作業を始めました (図 9)。数か月後、研究者らは 2 つのタンパク質を精製しました。高濃度のタンパク質は約 5 mg 生成され、カルシウムイオンによって活性化される発光タンパク質であるエクオリンと名付けられました。もう一つの「副産物」は、エクオリンが太陽光の下で濃い緑色に現れる前に液体クロマトグラフィーカラムから溶出され、グリーンプロテイン(GP、後にGFPに改名)と名付けられました。予想外にも、当時は取るに足らない「副産物」だったこの物質が、やがて生物科学史上の重鎮となったのです。 下村脩氏によるエクオリンの精製に関するいくつかの論文の発表により、ジョンソン研究室での3年間の客員研究員としての期間は、非常に実り多いものであったと言える。 1963年、下村は日本に戻り、名古屋大学水科学科の助教授に採用されましたが、2年後、クラゲの発光メカニズムをさらに研究するためにジョンソン研究所に戻りたいと考えるようになりました。下村脩氏は数年にわたるたゆまぬ努力の末、カルシウムイオンの制御下でのクラゲ毒の発光メカニズムを徹底的に解明しました(図10)。アポエクオリンは、好気条件下で小分子補因子セレンテラジンと共有結合して、生物発光能力を持つ安定したエクオリン中間体を形成する必要があります。そして、この共有結合は実際には過酸化物橋であり、一種の「内在酸素」です。この過酸化物結合はカルシウムイオンの刺激により急速に切断され、二酸化炭素を形成しながら明るい青色光を発します (図 10)。 図10: エクオリン発光の生化学的メカニズム さらに興味深いのは、セレンテラジンはウミホタルのルシフェリン(下村脩氏の有名な研究)と化学構造が明らかに類似しており、実際には「内在性ルシフェリン」であることです(図 11)。この瞬間、下村脩は、1961年夏、従来のデュボア理論に則ったクラゲ研究で行き詰まった理由に突然気づいた。まさに「終わりが原点に戻る、今気づいた」という感じだった。科学史のこの興味深い時代を研究するとき、私たちは有名な遺伝学者テオドシウス・ドブジャンスキーの有名な言葉を思い出します。「生物学においては、進化の観点から見なければ何も意味をなさない。」光るために 5 つの成分 (ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酸素、ATP、Mg2+ イオン) を必要とするホタルから、3 つの成分 (ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酸素) のみを必要とするウミホタル、そして、充電式バッテリーのように分子内に固有のルシフェリンと酸素を隠す発光タンパク質エクオリンに至るまで、自然淘汰による生物の進化は、まさに「海を渡る 8 人の仙人がそれぞれ魔法の力を発揮する」ようなものです。 図 11: エクオリンの補因子であるセレンテラジンは「固有ルシフェリン」です エクオリンの発光の生化学的メカニズムを発見した後も、下村脩は緑色タンパク質の副産物であるGFPを忘れませんでした。しかし、クラゲにおけるGFPの含有量は比較的低い。彼の予備的な見積もりによれば、GFPを精製し結晶化するための十分な原材料を得るには、何十万匹ものクラゲを回収する必要があるだろう。下村脩氏の科学研究への献身は、山を動かす玉公の精神を彼に与えた。 GFP をさらに研究するために、彼は十分な原材料が集まるまで毎年夏にフライデー ハーバーまで遠慮なく長い旅を続けました。 1962年から1974年まで、あっという間に12年が過ぎました。下村脩はジョンソンの研究室で最終的に十分な量の GFP を精製し、緑色の結晶を得ることに成功しました (図 12)。 GFPの発光メカニズムをさらに研究するために、下村脩氏は純粋なGFPタンパク質を100mg摂取する必要があると見積もったが、毎年夏に4万匹以上のクラゲを捕獲しても得られるGFPはわずか20mgだった。その後、彼は5年間にわたって知識を蓄積し続け、1979年にGFPの蛍光色素分子を予備的に特定しました(図12および13)。 1977年、70歳近くになっていたジョンソン教授は退職を決意したが、プリンストン大学は、単独で研究資金を獲得する能力が限られていた下村脩を留任させるつもりはなかった。ジョンソンは、生物学部門の指導者に、清水が仕事を見つけるのに十分な時間を与え、メインキャンパスから数マイル離れた一時的な研究室を提供するのに十分な時間を与えるよう説得することしかできませんでした。 図12:osamu shimomuraは、10年以上にわたってジョンソン研究所におけるクラゲGFPタンパク質の発色団の精製、結晶化、および予備的識別を完了しました。 ジョンソンの研究室は、タンパク質フラグメントシーケンステクノロジーをまだ習得しておらず、この分野で協力者を積極的に求めていません。タンパク質シーケンスを知らずに、GFP色素形成のOsamu Shimomuraの推論はかなり粗く(図13)、彼は発色団がGFPのアミノ酸側鎖からのみ来たかどうかについて決定的な結論を出すことができませんでした(補因子は必要ありません)。図13のGFPには、1990年代半ばの10年以上後まで、固有の蛍光発色団が含まれていた歴史を変えるブレークスルーが含まれていました。 図13:クラゲGFPタンパク質分子には、固有の蛍光発色団が含まれています 1981年、アカデミックコミュニティの多くの友人の助けを借りて、シモムラは、ジョンソン教授が退職してから4年後、マサチューセッツ州ウッズホールの海洋生物研究所(MBL)の上級研究者としてついに雇われました。それ以来、彼の研究は他の発光生物に移行し、クラゲのGFPはもはや関与していません。ここでは、長年の知識システムを使用して、オサム島の発見をクラジズの発光に関するいくつかの重要な発見を要約しています。 、生物発光を達成する。 Aequorinによって生成された光エネルギーは、生物発光共振エネルギー移動(BRET)を介してすぐに近くのGFPに伝達され、最終的に肉眼で見えるGFPグリーン蛍光を発します(図14)。 図14:クラゲはブレットメカニズムを使用して、エクオリンの青い生物発光エネルギーを近くのGFPに伝達します。出典:http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/gfp-ww/shimomura.html PrisherによるAequorinの分子クローニング 1960年代、ShimomuraとJohnsonがAequorinとGFPを発見したとき、分子生物学はまだ初期段階にありました。生物学者が特定のタンパク質の機能を研究したい場合、従来の「一方向ルート」のみを採用することができました。多数の標的種抽出サンプルを準備し、生化学的方法を使用してタンパク質を精製します。大量に人工的に培養できる生物または細胞株の場合、タンパク質精製に必要な原料は無尽蔵です。しかし、クラゲなどの海洋生物はこれまで人為的に栽培することはできず、実験で使用される純粋なタンパク質は、供給を確保するために労働集約的な継続的な漁業と準備が必要です。生態環境の変化により、標的種が固定水域に現れなくなると、タンパク質機能に関する研究が停止します。幸いなことに、遺伝コードの解読と分子生物学の中心的な教義の確立により、組換えDNA技術は1970年代後半に生まれ、ウイルスからの逆転写酵素は強力なcDNA分子クローンクローン技術を生み出しました。生物学者が標的タンパク質をエセリチア大腸菌のプラスミドにコードするcDNAをクローン化できるようになると、細菌を培養することにより大量の純粋なタンパク質を簡単に得ることができます。これは、基本的な機能研究に関する心配から彼らを解放するだけでなく、開発とアプリケーションをより効率的にします。 米国のジョージア大学のミルトン・コーマー教授は、1950年代から生物発光を研究しており、彼の初期にはレニラ(海のパンジー)に焦点を当てていました。 ShimomuraとJohnsonの画期的な作品の出版後、Cormierの研究室はその研究努力のいくつかをクラゲに変え始めました。 GFPストーリーの2番目の主人公であるダグラス・プラッシャーは、1983年にCormierの研究室に来て、ポスドク訓練の第2ラウンドを開始しました。以前のポストドクラル研究所では、Prasherは細菌の遺伝学に焦点を当て、当時は簡単ではなかった新しい分子クローン技術を首尾よく習得しました。 1982年、有名な実験マニュアル「Molecular Cloning:A Laboratory Manual」(図15)の出版により、遺伝子クローニング技術の普及が強く促進されましたが、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を含む多くの技術的手段はまだ発明されていませんでした。 図15:1982年のMolecular Cloning Laboratory Manualの初版の表紙 Cormierは、新人のPresherがAequorin遺伝子をクローニングするという課題を受け入れることを望んでいました。成功すれば、ラボが1晩で大腸菌を使用して生産できるエクトーリンタンパク質の量は、夏全体にわたって金曜日の港に挟まれたクラゲから浄化できる合計を超えます。単一のクラゲから調製できるmRNAの総量は高くなく、プラッシャーは金曜日の港に行って、オサム・シモムラのような多くのクラゲサンプルを収集する必要があります。 1985年、2回連続して蓄積の夏の後、PrasherはcDNAライブラリーを構築するのに十分なmRNAを抽出しました。その後、既知のタンパク質配列に基づいて設計された分子プローブを使用してcDNAライブラリーをスクリーニングし、5つのタンパク質アイソフォームに対応するAequorinをコードする6つのcDNAクローンを正常に分離しました。 Prasherがこれらの遺伝子をクローン化し、大腸菌で発現した後、彼は数週間にわたってタンパク質ゲル電気泳動のAequorinに対応するバンドを検出することができませんでした。 Cormierの科学的直観は、電気泳動検査は十分に敏感ではないと彼に言ったので、彼はすぐに技術者のRichard McCannにAequorinの生物発光テストの設計を支援するように頼みました。大腸菌の過剰発現により、カルシウムイオン色素であるAequorinの価格が大幅に低下し、すぐに一般的に使用される実験試薬になりました。 Aequorin遺伝子のクローニングに成功する勢いにより、Prasherは最終的に2回の長いラウンドのポストドクタートレーニングを完了し、1987年10月に米国マサチューセッツ州のWoods Hole Oceanographic Institution(WHOI)で独立したアシスタント研究者として雇われました。 GFPタンパク質とmRNAの豊富さがAequorinの存在量よりもはるかに低いことを考えると、Prasherは毎年金曜日の港に行く必要があります。 PrasherはWHOIで独立していましたが、新興企業の資金が限られているため、大学院生、ポスドクの仲間、または技術者を募集することができなかったため、クラゲのGFP遺伝子をクローンするために独力で戦いに従事しなければなりませんでした。同時に、彼はGFPタンパク質が蛍光に補因子を必要とするというオサム・シモムラによって提案された仮説について懐疑的でした。彼は、GFP遺伝子が得られ、大腸菌で発現すると、緑色蛍光が直接観察されると、組換えDNA技術を使用してGFP遺伝子をあらゆる種の遺伝子と融合させることにより、蛍光を使用して細胞内のタンパク質産物の発現を配置できることを想像しました。このエキサイティングなアイデアに基づいて、Prasherはいくつかの研究基金申請を提出しましたが、それらのほとんどはレビュー委員会によって拒否されました。米国癌協会のみが、200,000ドルの資金提供を提供することに同意しました。 1989年初頭、ほぼ2年間の勤勉さの後、PrasherはPGFP1と名付けられたクラゲ遺伝子ライブラリーからcDNAクローンをスクリーニングしました。プラスミドには、168のアミノ酸をコードする配列が含まれていました。 GFPタンパク質の全長が238アミノ酸であることを知って、Prasherは、このcDNAの5 'と3'の両方の端が不完全であることに気付きました。この168アミノ酸タンパク質シーケンスは、彼が協力したWard Laboratory(William W. Ward)に大いに役立ちました。 GFPクロモフォアに関する1979年の1979年の作業を大幅に改善し、GFP内の3つの接続されたアミノ酸側鎖(Ser65-Tyr66-Gly67)が緑色蛍光を生成する分子基盤であると判断することができました(図16)。しかし、プレシャーがGFP蛍光を分子局在化のツールとして使用したい場合、GFPの全長cDNAをクローンする必要がありました。 図16出典:Cody、CW、Prasher、DC、et al(1993)生化学32:1212-1218 ChalfieとRoger Tsienは、GFPラベル付け技術を作成しました Prasherが再びクラゲを集めて新しいcDNAライブラリを構築し始めたとき、GFPストーリーの3番目の主人公であるMartin Chalfieが予想外の方法で登場しました。米国コロンビア大学のChalfie's Laboratoryは、Caenorhabditis Elegansの触覚神経生物学の研究に専念していました。 1989年4月25日、彼はいつものように、火曜日の正午の講義局に出席しました。 Tufts UniversityのPaul Brehmは、さまざまな生物の発光タンパク質を導入しました。 Chalfieは、カルシウム色素として使用されるAequorinのことを聞いていましたが、GFPを聞いたのは初めてでした。紫外線または青色光に励起されるモノマーGFPタンパク質は、おそらく補因子を必要とせずに蛍光を放出する可能性があります。この機能は、これに非常に興味があったChalfieを励ましました。 C. elegansには完全に透明であるという自然な利点がありますが、当時のいくつかの一般的に使用される遺伝子およびタンパク質発現の局在化手法には長いサンプル調製ステップが必要であり、染色試薬は線虫の体に浸透するために必要なため、生きている動物を直接観察するために使用できませんでした(図17、左)。 238のアミノ酸しかないGFPが本当に輝く可能性がある場合、研究者は分子生物学的方法を使用して、それを対象の線虫遺伝子と融合させることができます。 Fusionタンパク質のGFP蛍光標識を介して、遺伝子が発現する細胞が発現する顕微鏡下で直接観察できます。翌日、Chalfieは科学者がクラゲGFP遺伝子を正常にクローニングしたかどうかを調べるために多くの電話をかけました。最終的に、彼は、WhoiのPrasherだけが彼に望んでいた答えを彼に与えることができることを発見しました(図17、右)。 図17:透明なCaenorhabditis elegansは、動物の発達中の細胞分化と機能の研究に適しています。 GFPテクノロジーの前のいくつかの遺伝子発現局在法には、サンプル調製が必要であり、生きている線虫を直接観察するために使用できませんでした。 Bramの講義からGFPの発光特性について学んだ後、Chalfieは1日の電話でPrasherに連絡しました。出典:Chalfie、M。(2008)ノーベル講義。 ChalfieとPrasherは電話で非常に良い会話をしました。彼らはGFPのアプリケーションの見通しについて同様のアイデアを持っていましたが、PrasherがGFPの完全なcDNAクローンを取得するまで、彼らの協力は開始できませんでした。以前に細菌プラスミドで構築されたクラゲ遺伝子ライブラリーの平均断片が十分に大きくないことを考慮すると、Prasherはλファージを使用して新しいcDNAライブラリーを構築することにしました。 2年後、彼は238のアミノ酸をコードする完全な配列を含むλGFP10クローンをスクリーニングして取得しました(図18)。残念ながら、Prasherはこのマイルストーンを祝う気分になりませんでした。(1)アメリカ癌協会からの研究資金がなくなっており、彼の最新の資金申請は繰り返し拒否されました。 (2)彼は発現のためにλGFP10を大腸菌に移したが、結果として得られるGFPタンパク質は顕微鏡下で蛍光を発することができなかった。 (3)Whoiの彼の同僚は、彼の遺伝子クローン作業にほとんど興味がなく、新しい資金がなければ、彼はテニュアレビューに合格する希望を見ませんでした。 Prasherは最初にGFPのcDNAシーケンスを公開することを決定しましたが、この論文は提出の開始からスムーズに進むことはなく、1992年2月に公式に公開されるまでに1年近くかかりました。 図18出典:Prasher、DC、et al(1992)Gene 111:229-233 プレッシャーは、論文が公開された後、電話でChalfieに連絡しようとしましたが、残念なことに、Chalfieは結婚したばかりだったので、ユタ大学の妻の研究室で学術休暇を取得していました。 PrasherがGFPストーリーの最後の主人公であるRoger Tsien教授であるChalfieに連絡できなかったために、Prasherに連絡することができなかったため、1992年5月にPrasherの新しい論文を読んだとき。マーカータンパク質を導入するよりも、研究対象の細胞にマーカー遺伝子を導入する方がはるかに簡単です。また、思慮深い人であるQian教授は、Presherの手にcDNAクローンの価値を一目で見ることができます。 Prasherは、Qian教授に電話で、資金調達の申請が困難なため、すぐにWhoiを去り、米国農務省で働き、GFPの研究に別れを告げると語った。 Prasherは、GFP遺伝子のクローニングをすぐに共有することをいとわなかった。残念ながら、Qian教授の研究室には多くの化学の専門家がいましたが、分子生物学の技術を習得した人はいませんでした。彼は、新たに募集されたポストドクターの仲間であるロジャー・ハイムが1992年10月に報告されるまで待たなければなりませんでした。この5か月の遅延は、ChalfieがGFPをほとんど逃した状況を覆しました。 図19出典:Chalfie、M。(2008)ノーベル講義 Chalfieは、1992年秋の学期が始まる前にコロンビア大学に戻りました。 9月上旬、1年生の博士課程の学生であるGhia Euskirchenは、Chalfieの研究室での最初のローテーションを望んでいます。 ChalfieがJiaが大学の工学部の蛍光に関連する修士論文を完成させたばかりであると聞いたとき、彼は3年後にPrasherからのニュースがなかったことを嘆きざるを得ませんでした。彼は、GFPに関連するプロジェクトのデザインアイデアを見つけるために、彼女と一緒にコンピューターの文献を検索することしかできませんでした。 Chalfieが今年の初めにPrasherが発行した完全なGFP遺伝子シーケンスを見たとき、彼は大喜びし、すぐにPrasherに電話で連絡して計画されたコラボレーションを再開しました。 PrasherのGFPクローンを取得した後、Chalfieは、PCRテクノロジーの代わりに分子クローニングプロセスでエンドヌクレアーゼのみが使用されているため、WHOIを含む多くのアメリカの研究機関は、Harvard、a a a sequed ase sequp10を共有する必要がありましたGFPコーディングシーケンスの端は、5 'スタートコドンの上流の25の追加塩基ペア(図19の右上、赤でマークされた)を含む。 Chalfieの分子生物学の直観は、両端の余分な配列が大腸菌のGFPの発現を妨げる可能性があると彼に言ったので、彼は最初に分子クローン実験を行うJiaに指示しました。 数週間後、JIAはGFP発現プラスミドを含む多くのコロニーを取得しました。彼女は、ChalfieがGFPのタンパク質産物が蛍光を直接放出できると信じていたので、培養皿を馴染みのある工学部に戻し、そこに蛍光顕微鏡を使って運を試すかもしれないと考えました。 1992年10月13日、Jiaの実験室ノートブック(図19、左)は、この予期せぬ「ユーレカの瞬間」を完全に記録しました。当然、Chalfieは彼がそれを見たとき非常に興奮していました。数日間連続して、彼はどこでもGIAが撮影した顕微鏡写真を披露しました(図19、右下)。実験結果は、GFPタンパク質がクラゲの補因子または変換酵素のない別の種の細胞の緑色蛍光を自発的に放出できることを明確に証明しました。 図20:Chalfie Labは、組換えDNA技術を使用して、クラゲGFP遺伝子を線虫Caenorhabditis elegansのタッチ感受性ニューロンの転写プロモーターにリンクし、GFPの緑色蛍光を使用して個々の細胞を特異的にマークすることができることを成功裏に実証しました。 出典:https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/popular-chemistryprize2008.pdf この実験を完了した後、Jiaはすぐに別の研究室に回転し、Chalfieは技術者に新しい実験を試みるように頼みました。まず、GFP遺伝子をC. elegansのタッチ感受性ニューロンの特定のプロモーターに接続し、次にマイクロインジェクションを使用して、新しく構築されたプラスミドをマチュアヌマトーデスのゴナドに移します。 GFPの発現が成功する限り、雌雄同体線虫によって生成される次世代の幼虫のタッチ感覚ニューロンは、顕微鏡下で緑色蛍光によって照らされます(図20)。この成功した画期的な実験は、科学雑誌の表紙記事の形で科学の歴史に最終的に記録されました(図21)。 図21出典:Chalfie、M。(2008)ノーベル講義 何年も後を振り返ってみると、Giaの「Eureka Moment」はPrasherに属していたかもしれません。そして、彼を見逃した「犯人」は、おそらくλGFP10の5 '末端にある余分な25塩基ペアでした!単一細胞の原核生物として、大腸菌は比較的単純な遺伝子転写調節を備えており、スイッチの効果を達成するためにプロモーターと調節シーケンスのみを必要とします。しかし、多細胞真核生物としてのクラゲの転写調節メカニズムははるかに複雑であり、プロモーターが複数の短距離および長距離エンハンサーと調節シーケンスと相互作用する必要があります(図22)。クラゲの5 '調節配列が大腸菌のプラスミドに運ばれると、細菌プロモーターの「コンテキスト」を破壊し、したがって標的遺伝子の正常な発現を妨害する可能性があります。 Prasherが1991年に協力者を見つけることでPCRテクノロジーを使用できた場合、GFP研究の歴史は書き直されていたでしょう。 Ye Shengtao氏の有名な短編小説「Threeまたは5 Bushels」は中国の中国の教科書に含まれていました。ここでタイトルを模倣することで、プラッシャーがノーベル賞を逃したという悲劇的な物語を要約することができます。 図22:大腸菌におけるGFP発現を干渉する25塩基対の25塩基対の潜在的な分子生物学的メカニズム。 Qian Yongjianは、Geimが到着した直後にPrasherに再び電話をかけました。 Prasherは、約束されたGFP遺伝子クローンを送信し、1か月前にChalfie Laboratoryがクローンを受け取ったことを彼に知らせました。 Qian Yongjianが最初にすでに遅れていたとき、彼はChalfeeとの健全な競争を始めることにしました。双方は情報を交換し、互いの研究の方向性を積極的に避けました。チアン教授は、GFPが有機化学の深い知識を持って、GFPが自分で光を放出できることを証明したことを知った後、アプリケーションの見通しに希望に満ちていましたが、3つのアミノ酸側鎖SER65ティル66-GLY67が、一時的に炭酸を描写するためにcyclogoreを形成するためにcyclogeを形成するために、酵素触媒なしで発生することは困難でした(図23)。 Qian教授は2つの化学経路しか想像できませんでした。(1)2つの水素原子が結合して水素ガスを形成してから放出することを想像できます。 (2)2つの水素原子を運ぶために酸化剤が必要であり、実験者が直接操作できる唯一の酸化剤は空気中の酸素です。 Qian教授は、厳密に嫌気性の一定温度シェーカーにGFP発現プラスミドを含むGeim Culture E. coliを提案しました。彼らは、電気泳動ゲルで正常な分子量のGFPタンパク質が見られることがあるが、これらの細菌は蛍光を放出できないことを発見して驚いた。細菌培養が2時間好気性環境に戻されたとき、緑色の蛍光が再び見ることができました。これに基づいて、Qian教授はGFPによる発色団の自発的形成のための詳細な化学メカニズムを与えました。過酸化水素が生成されるという理論的推論は、2006年まで他の研究所によって確認されませんでした(図23、右上)。 図23出典:Tsien、Ry(2008)ノーベル講義 Qian教授は、野生型GFPの励起スペクトルには、高と低い2つのピークがあるという事実にも困惑していました。紫外線は、青色光よりもGFPの蛍光をより効果的に刺激する可能性があります(図23、左下)。彼の有機化学の直観に基づいて、彼はセリン65(Ser65、S65)の側鎖が二重ピークを引き起こす鍵であると推測しました。議論の中で、Molecular Biologyの専門家であるGeimは、部位指向の突然変異誘発を使用してセリン65を他のアミノ酸に置き換えることにより、この仮説を検証できることをQian教授に思い出させました。セリンがスレオニン(S65T)に置き換えられたとき、紫外線励起ピークは消失し、このGFPの青色光による蛍光励起効率は野生型GFPの8倍でした(図23、左下、右下右)!サイト指向の突然変異誘発により、Qian Yongjianの研究室がGFPを包括的に改善するための水門が開かれました。彼らは、青色蛍光タンパク質(BFP)、シアン蛍光タンパク質(CFP)、黄色の蛍光タンパク質(YFP)などを連続して発射し、実験的生物学者の「パレット」にカラフルな色を追加しました(図23、右下)。 2008年のノーベル化学賞は、最終的にオサム・シモムラ、ダニエル・チャーフィー、ロジャー・ツィエンによって共有されました。長年にわたって学界から離れていたプラッシャーは、さまようとねじれやターンの生活を経験し、ノーベル賞の候補者の数が限られているため、委員会に好まれませんでした。さらに残念なことは、金曜日の港の近くの水域での油抽出によって引き起こされる環境汚染が継続したため、1990年代半ばから輝くクラゲが完全に消えてしまったことです。 おすすめの読み物 [1] Pieribone、V。&Gruber、DF(2005)Aglow in the Dark:The Revolutional Science of Biofloorescence、Belknap Harvard。 [2] Shimomura、O。et al(2017)発光追跡:クラゲ、GFP、およびノーベル賞への予期せぬ道、ワールドサイエンティフィック。 【GFPディスカバリー歴史講義ビデオ】 リンク1:https://youtu.be/ozjjnnvdzyc リンク2:https://www.bilibili.com/video/bv17k4y1u7vv この記事は、WeChat Publicアカウント「Medicine Times」から複製することが許可されています。著者は、「Fanpu」が公開されたときに2回改訂しました。 出典: ファンプ |
<<: アスピリンを長期服用する場合、副作用を軽減するにはどうすればよいでしょうか?
>>: エアコンを長く使っていると効きが悪くなると感じたことはありませんか?ついに理由が判明!
推薦する
象の幽霊と機械の戦いの歴史
© ウィキメディアリヴァイアサンプレス:私は個人的に、海のクジラであろうと陸上のゾウであろうと、巨大...
最もホットなeスポーツイベントに参加してみませんか? Acer V5-591G EDG スペシャルエディションの起動体験
おそらく、eスポーツゲームの大部分は、ゲーム体験の面でPCゲームの魅力を十分に反映できていないが、ア...
この種の化石は岩石層の「時間指標」と呼ばれています
地球は、長い地質学的発達と進化の過程で、動物、植物、微生物を含む多数の古代の生物を支え、増殖してきま...
植物の根は上向きにも伸びるのでしょうか?科学者が植物の重力感知の新たなメカニズムを解明
制作:中国科学普及協会著者: 李 銀 (中山大学生命科学学院)プロデューサー: 中国科学博覧会生物は...
電気オーブンでグリルチキンウィングを作る方法
通常、鶏の手羽先はオーブンやトースターオーブンで焼きますが、今回は食品の専門家が電気オーブンで鶏の手...
ニベの調理方法
生活の中では一般的な食べ物がたくさんあるので、自分の好みに合わせて食べ物を選ぶことができ、食べるとき...
iPad miniは「役に立たない」が、それでも欠かせないものになった
米テクノロジーサイトCnetは10月19日、 iPad miniの販売が大画面のiPhone 6によ...
パナソニックのエアコン技術は復活できるか?
「数秒で起動、強力な冷暖房」は、広州で終わったばかりのパナソニックの2015年エアコン新製品発表会...
春節祭のマスコット、ロン・チェンチェンの鼻は「中国最古」から来た?
昨年12月、CCTV 2024春節祭のマスコット「ロン・チェンチェン」が正式に発表されました。龍は中...
AIにおける新たなブレークスルー! 1歳未満で子供の「見えない殺人者」を特定、正確率は80%以上
自閉症は子供たちの「見えない殺人者」になりつつある。世界保健機関(WHO)のデータによると、 100...
蒸しターボット
蒸し鰈は宴会で最もよく食べられる料理であるだけでなく、栄養価の高い料理でもあります。この鰈を食べるこ...
中国では状況が変化:アイスバケツチャレンジは慈善活動から離れつつある
希少疾患である筋萎縮性側索硬化症(ALS)への認知度を高めることを目的とした「アイス・バケツ・チャレ...
300元でプライバシーを買うことはできますか? ! 「箱を開ける」ってどれくらい怖いですか?
あなたのプライバシーは依然として安全ですか?自分の名前、年齢、住所、写真、身分証明書番号、携帯電話番...
高級車に再び品質問題が発生。レクサスはなぜ頻繁にリコールするのでしょうか?
最近、中国国家品質監督検査検疫総局は12月16日に発表を行い、トヨタ自動車投資株式会社が中国国家品質...